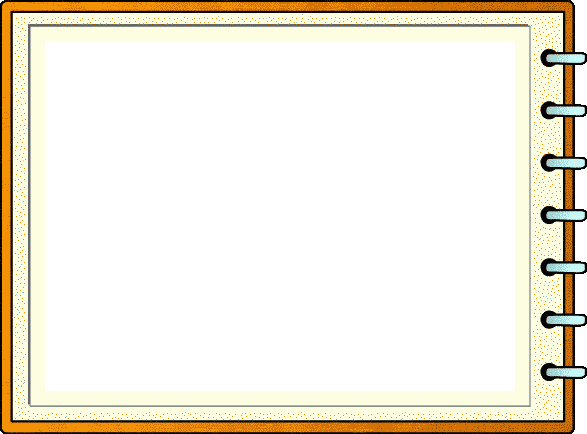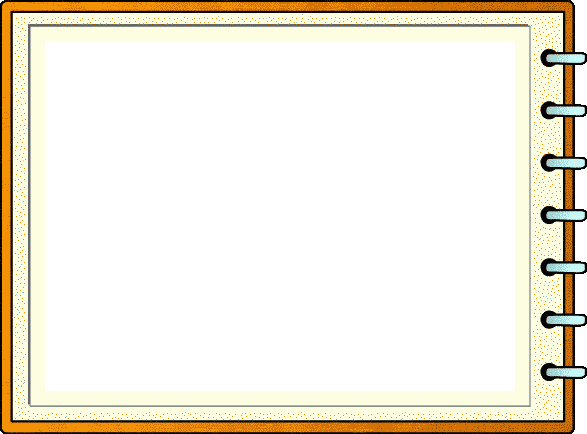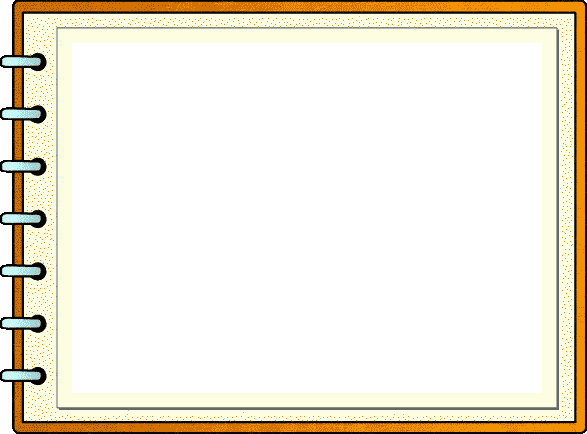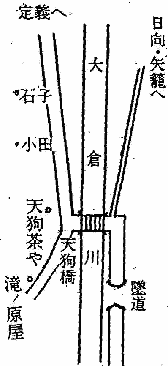天狗茶屋付近
定義街道一番の景勝地
天狗橋
大倉川の両岸から岩盤が張り出して川幅が狭くなった所に、太い杉丸太三本を渡し、両袂を土で覆い土橋のようにし、杉丸太には横に板を桟のように打ちつけた簡単なものだったといわれている。
大正時代末期手すりのある木橋に架け替えられた橋の下は狭いところを水が勢いよく滝になり音をたてて流れ落ちていた。
天狗茶屋(17・4キロ)
天狗橋を渡った南岸にあった茶屋で、この先定義までは茶屋はなかった。手の切れるような冷たい水の湧いた清水を利用して「ところてん」の商売をしていた。天狗茶屋の「てんよ」といって有名だった。
昭和36年、大倉ダムが竣工したことによって、ここから海老沼までが水没(水没家屋58戸)したのである。
小田・石子
小田には人家が一軒あり、土地では「こうだ」とよんでいた。曲がりくねった石ころの多いだらだら坂道が続く、間もなく石子の集落で道沿いに二軒の家があった。
石子を過ぎて少し行くと、右に分かれる道があった。この道は吹越(ふっこし)街道といって、大倉川を渡って岩出山方面に通じていた。川の向かい側に六角原という原があり、昔六体の地蔵が祀られていたということである(何時のころかわからないが、この六体の地蔵は白木・下倉・青下・日向・矢込・切払に一体ずつ分けて祀ったといわれている)。
新道
▲定義へ
▼畑前・仙台へ